ベッドルームミュージックの台頭
2010年代後半から現在にかけて、Boy PabloやClairoなど、シンガーソングライターがDIYで楽曲制作をする「ベッドルームミュージック」が音楽界に浸透してきた。SNSの成長、楽器・録音機材の進歩や低価格化、移動や人員のコストがかからないこと、そして何より自身が好きなタイミングで音源制作ができることなど、要因を挙げるときりがない。
極めつけは、2019年突如として現れたニューカマー、ビリー・アイリッシュによるベッドルームミュージックのポップ化だろう。”Bad Guy”が収録されているデビューアルバム「When We All Fall Asleep, Where Do We Go?」はティーンを筆頭に話題沸騰となり、さらにはグラミー賞主演4部門の全受賞の快挙も成し遂げた。

そして、新型コロナウィルスの流行というもあり、期せずして世界がベッドルームミュージックの渦に巻き込まれている。
それに伴い、2010年代のUKロックバンドは90~00年代と比べかなり尻すぼみを感じる。KasabianやThe Libertinesのような時代を席巻したバンドは現れず、このまま時代に流されていくであろうと思われた矢先、UKロックバンドを復活させるのではないかという期待を抱かせる超新星が6年前に現れた。
The Snuts

The Snutsというバンドをご存知だろうか。2015年に中学の同級生で結成されたスコットランド出身の4人組バンドだ。今現在、2020年代のUKロックを背負うバンドの筆頭として挙げられている。
2016年リリースの”Glasgow”のデモ音源、2017年リリースの自主制作EP「THE MATADOR EP」をきっかけにイギリス国内で注目を集める。そして翌年にはTRNSMTフェスティバルに出演、ここまで順調に階段を登って行っている彼らだ。
どことなく垢抜けない出で立ちの4人だが、出で立ちに似合わず、曲の完成度が非常に高い。
お分かりだろうか、まず声がUKだ。鼻にかかった色気のあるハスキーボイスはArctic Monkeysのアレックス・ターナー、The Kooksのルーク・プリチャードを思わせる。
演奏自体は粗削りな側面もあるが、 展開の落としどころを含めた全体のダイナミクスが非常にわかりやすく、5分の楽曲とは思えないスッキリさだ。結成1年とは思えない熟練さである。彼らのような才能溢れるバンドを定期的に生むイギリスならではの音楽の土壌、畏怖の感情が沸き起こる。
そして満を持して今年3月、1枚目のアルバム「W.L.」がリリースされた。ストレートなUKロックを主体に、甘い曲調で聴かせるナンバーやダンサブルでソウルフルなナンバー、様々な歴代のUKバンドからの影響を感じさせる彼らのアルバムを今回は紹介する。
UKロックの醍醐味が織り交ざった一作

タイトルのW.L.とは、’Whiteburn Loopy’の略、和訳すると「ウィットバーンの悪ガキども」だ。ウィットバーンとは彼らが生活していた場所であるスコットランド内の小さな町で、当時の生活をタイトルに現したのだろう。
今記事ではDisc1の計14曲の中で印象に残った楽曲を書き連ねていく。
アルバムのトップを飾る”Top Deck”、頭を飾るにしては結構思い切った1曲ではないか。落ち着いた、渋みのあるボーカルが全面に出た曲だ。この曲を聴く限りUKロックではないし、そもそもバンドですらない。
序章とでも言うべきか。次曲”Always”へ移行しよう。
スコットランドチャート1位を獲得した、先行リリース楽曲群の内の1曲。やはり1曲目”Top Deck”はフリだった。しっかりとUKロックだ。どっしりとしたミドルテンポ、最近流行りのベタベタに潰れた音色のギター、しゃがれが増したボーカルの短調なメロディが印象に残る。
こういったギターリフとメロディで攻めるタイプの曲はアップテンポでキャッチーに作られがちだが、敢えてこのテンポで攻めている彼らの6年の重みを感じた。
キャッチーではなくカッコよさに振り切ったダンサブルな曲だ。KasabianやArctic Monkeysなど、90~’00年代以降のUKロックの色を感じる。
元々歪み気味の声を持つボーカルが、さらに歪みのエフェクトを加えている部分を筆頭に、各楽器の音作り、ドラムフレーズなど各パートが高次元のアレンジを加えていることは明白だ。
ついに来た。彼らの処女作でもある”Glasgow”の本チャンだ。
語彙力が0になり申し訳ないが、最高だ。
デモ音源と異なる点で明瞭なのはテンポだろう。絶妙すぎるテンポアップが、アンセムとしての存在感を倍増させている。
今作の中では最もストレートなギターロックナンバーだ。近年でUKのストレートなギターロックバンドと言えばCatfish And The Bottlemenが頭に浮かぶが、彼らよりもサウンドがいなたく、同じジャンルでまとめるのはあまりにも勿体ない。
また、完全な個人の感想になるが、歌詞の中で繰り返し多用される「I’ll always love the way that you say Glasgow」という節の最後の「Glasgow」をイントロでは音程を合わせ、イントロ以外は音程を合わせないことで言葉として使用している感じが滅茶苦茶に好みだ。
個人的には、”Glasgow”がアルバムのド真ん中に位置していたため、その後の曲が少し心配だったが、それは素人の杞憂に過ぎなかった。
今作最大のシンガロング曲だ。将来出演するであろうReadingやGlastonburyでボーカルがギターしか弾かないのはもう目に見えている。
アルバムをA面で満足させず、盛り下げない役割と、後半にスムーズに移行する役割が両立している、非常にバランスの取れた楽曲だ。
最後に紹介する”Elephants”は、”Always”同様先行リリースされた楽曲群の1つである。PVがかなり印象的な1曲で、メンバーが演者となり踊り狂う謎の内容となっている。4人の横に名前が表示されていて、各メンバーの名前を覚えるには最適のPVだ。
私が最初にThe Snutsと出会ったのがこの曲だ。正直に言うと、この後に聞いた”Glasgow”で「このバンドはどっちだ?」となったのは否めない。
他の楽曲とは少々色の異なる、今までにはなかったインディー感が曲全体を覆っている。ただ、このインディー感は決して突拍子もないものではない。The Kooksのようなギターアプローチ、KasabianのようなコーラスアプローチとしっかりとUKの土壌を感じさせるアレンジワークだ。
2020年代のUKロックを背負うのはこいつらしかいない
これまでに紹介したThe Snutsの「W.L.」だが、実はもう既に1つの快挙を達成している。
今作は2007年のThe Viewのデビューアルバム「Hats Off To The Buskers」以来、14年ぶりにデビューアルバムで全英1位を獲得する快挙を達成したのだ。
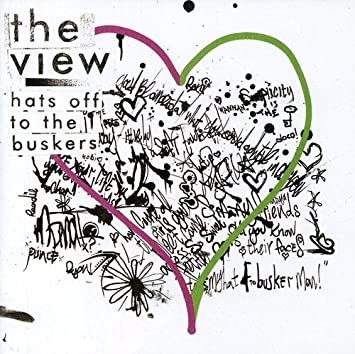
そして現在はコロナ禍により延期などを挟んではいるものの、英国内を中心に精力的にライブ活動を続けている。これからは大型フェスの常連になっていくだろう。どこのステージで演奏するかが論点になってくる。
ただ、先述のThe ViewsやThe Kooks、Razorlightなど、鮮烈なデビューを果たしながらデビュー当時を超えなかったUKロックバンドは数多いる(それらを悪く言うつもりは毛頭ない)。The Snutsにはその数多にはなってほしくはない。しかしその心配も、今作「W.L.」を聴けば安心するだろう。
UKロックを土壌に据えた上で際立つ楽曲群のジャンルの多彩さ、若さを感じつつも完成度の高い1曲1曲。これからのUKロックを背負って立つという議論においては、今作によって彼らが頭一つ抜け出したのではないだろうか。
The Snutsの日本での一素人フォロワーとして、これからの動向を逐一チェックしていきたい。
まずは日本来い。









