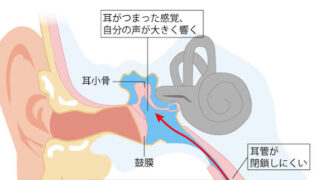いきなりだが、まずは見て欲しい動画がある。
これを見て何も感じなかった方は今すぐブラウザバックだ。この記事を見ても時間の無駄でしかないだろう。向こう1週間のスーパーの値引き品の予想をする方がまだ有意義だ。
これを見て意味不明と思った方、不気味さの中に沸き起こる興奮を感じた方は今記事を是非読んでみて欲しい。きっと有意義な時間となるだろう。
この”世界タービン”という曲は、1954年出生の御年67歳、大閣下である平沢進のフラッグシップソングの1つだ。ちなみにこの曲、星野源のANNでも取り上げられたことがある。
著名ミュージシャンを含む一部の音楽ファンの間でカルト的な人気を誇る平沢進だが、2年前のフジロック’19にてその存在が一般の音楽ファンに顕わとなった。彼は何気なく訪れたレッドマーキーのファンを食い物にした。筆者もそのライブの配信にて彼に心を預け切った1人である。そう「馬の骨」になってしまった。
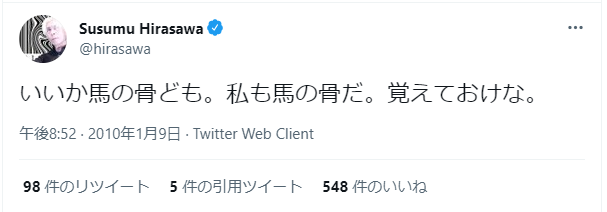
馬の骨ってなんやねんと思う方もいるだろう。平沢進及びそのフォロワーの呼称のことである。フジロック’21にて2度目の出演を果たし、そのライブ配信を見た私は、馬の骨レベル1からレベル2に進化した。
誰にも理解し得ない独特すぎる音楽観とIQ500の言語センスを駆使したTwitterで音楽ファンを魅了する平沢進について、馬の骨レベル2なりにフジロック’21の彼のパフォーマンスについて少しばかり書き連ねていく。
平沢進とP-MODEL

まずフジロック’21のライブ配信について書くにあたり、欠かせない1つのバンドを“ほんの少しだけ”紹介する。それが1980年代のテクノポップブームを牽引したバンド「P-MODEL」だ。1979年、平沢進を主導に結成された同バンドは、デビューから当時流行していたテクノポップの筆頭バンドとしてかなりの人気を誇っていた。XTCやVan Halenの前座を務めるだけでなく、武道館公演も果たしているように実績も十二分だ。
上記画像は1枚目のシングル“美術館で会った人だろ”のジャケットである。ポップなリードシンセと不協和音の合いの手シンセが脳裏に強く焼き付けられるだろう。まるでストーカーを描いているような恐怖すら感じる歌詞は平沢進節が全開で、Twitter上で定期的に歌詞考察がなされている。
その後、凍結や改訂、培養など(いずれも活動休止のことである)紆余曲折を繰り広げた21年間、計12枚のアルバムを世に出したP-MODELは現在幕を閉じ、2004年以降は核P-MODELとして平沢進が単独で不定期の活動を行っている。
先述のように私は馬の骨レベル1だった。知らない曲の方が多い現状だ。ただ、その中でも私は核P-MODEL期の曲が抜けて好きである。その中でもレベル1らしく、3枚目のアルバム『гипноза』より超有名曲でもある“Timelineの東”を紹介する。
平沢進の中では比較的わかりやすくキャッチーな曲だ。余談だが、右でギターを弾いている人間らしきものはPEVO1号と呼ばれており、少なくとも人間ではない。
まるで行進しているかのような頭拍を打ち出すビートにテクノなシーケンスとクラシカルなシンセが絡み合い、そしてそれらを土台に音価の長いメロディラインと伸びやかな歌声が我々を多幸感の渦へと誘う。
もちろんメロディやアンサンブルも特筆すべき点が多く存在するが、私は敢えてギターソロを推したい。
ここでは、ピックを用いたタッピングを駆使しソロを奏でている。珍しい奏法だ。もしピッキングのみで同ソロを弾いたならば、ただの間奏としてのギターソロになってしまうだろう。しかし、彼はピックを用いたタッピング奏法を活用することで他トラックの連続するフレーズとの親和性を持たせている。そのため、ギターソロとして際立ちつつも、変な浮き方をしていない。その上でキャッチーかつクールなこのフレーズセンス、脱帽だ。
個人的には平沢進のギターソロの中でもトップクラスに好きだ。彼のギターにおける引き出しの多さ、そして演奏力の高さが垣間見える1シーンだろう。
’19とは明確に異なった楽器陣の圧とライブ前半のダークさ
さて、P-MODELについて少し取り上げたところで本題のフジロック’21に移りたい。それに際し、ライブ終演後数時間でアップされていた、セットリストが原曲でまとめられている動画を付属しておく(著作権の関係上一部はないが)。正直仕事が早すぎて引いた。馬の骨レベル100だと私は推測する。
’21は’19と変わらず「平沢進+会人」での出演だった。しかし、’19と明確に異なる点があった。それはドラマーの出現(出演)である。これは2019年のBattles来日公演でOAを務めた時に初披露した新編成であるが、この部分は非常に大きな変化だっただろう。
打ち込みだったドラムから生ドラムに変わったことにより、生音感及び楽器の圧が前回よりも大きく増していたように思う。特に、6曲目に披露した核P-MODEL期の楽曲“TRAVELATOR”では、配信上でも伝わってくる生ドラムならではの迫力だった。初聴きの曲ながら私的平沢進ランキング上位に食い込んだ楽曲だ。
余談だが、前曲“Solid Air”にて機材トラブルが発生しており(おそらく平沢進のギターが鳴らなかったのだろう)、“TRAVELATOR”ではそれに対する怒りの様なものを感じた。もっとも、私は楽曲の途中まで機材トラブルではなく演出の1つだと思っていたのだが。
’21では“Parade”を軸に明確に前後半が分かれていると個人的には考えていて、前半は非常に厳かでダークなテーマとなっていた。ただ、その中でも3曲目に披露した“ENOLA”のような楽曲を混ぜてくれていたのは非常に嬉しかった。 上記動画は’21のものではないが、今楽曲の雰囲気は伝わるだろう。おさらいがてら一聴していただきたい。
同楽曲も短調で進み、厳かでダークな雰囲気を持っているのは間違いない。ただ、他の前半の楽曲とは異なり、わかりやすく「ノれる」。私的な偏見も否めないが、私にとってこの楽曲はダークさ、不気味さを通り越している感覚がある。歌詞に何度も登場する「Ai Yai Yai」なんて一周回って陽気に聴こえるし、カルト的な面も感じる。
ミーハー族の馬の骨にとっては、「結構物々しいライブの入りだな」と思っていたところの今楽曲だったため、やっぱり彼のライブは気を抜いていられないと自分の中で引き締まった感覚があった。
万人を取り込まんとするセットリスト後半
さあ、後半だ。12曲目として演奏された、古参族もミーハー族も認める名曲「Parade」を皮切りに、ニュー馬の骨を手に入れるべくキャッチーで開けた後半の始まりだ。
「パレードやるんかい!」と思わず突っ込んでしまった。’19でこれでもかというほど万人向けの楽曲を披露していたからだ。ただ、前半のダークさから段々と光を漏らしていく楽曲としてはちょうどいい。その直後の曲に演奏した、’19で披露済みの意味不明な楽曲“夢見る機械”とも良い繋がりを感じた。
ここあたりからテスラコイルが火を噴くのだが、「またやってるわね」と親が子を見るような気持ちでテスラコイルが放電する様を見ていたのを覚えている。
終盤のラストスパートは今思い出しても鳥肌だ。アツすぎるドラムからの“Big Brother”、個人的に一番のハイライトだ。今楽曲は2パターン存在し、無印Ver.と可逆分離態様Ver.がある。’21では後者を披露したが、この瞬間私は心の中でガッツポーズした。前者はゴリゴリのテクノソングだが、後者はバンドサウンド感が強く、フジロックで演奏するとすれば間違いなく後者の方が映えると考えていたからだ。
既にこの時点で腹八分目だった私は、これまた神曲として名高い“救済の技法”をデザート代わりに楽しむという斬首されてもおかしくないレベルの贅沢を犯してしまった。唯一の反省点であろう。
終盤には前半のダークさは完全に振り払われていた。光が完全に我々を覆ったと同時に、今年にリリースされた新譜『BEACON』からのリード曲“TIMELINEの終わり”を締め曲として配信は終わる。まるで天国へ到達したかの様だった。その時の平沢進には後光が差していたことは言うまでもない。イントロのフレーズと歌詞中の「淡々と降るフィナーレの雨」でこの時間が終わることを察し、そして彼に感謝し、泣いた。
“TIMELINEの終わり”の原曲は思ったよりリバーブ感がなく、比較的ドライでミニマルな楽曲だ。しかし彼の専売特許ともいえるストリングス系のシンセ、そして何より彼の浄化作用を持つ歌声が聴く人を優しく包み込む。平沢進をこれから知る人には是非おすすめしたい楽曲の一つである。
衰えることを知らないそのクオリティ
’19では配信で観たとは思えない感動を覚えたが、’21では平沢進の楽曲の多彩さとその安定感にただただ驚かされた。いくつになっても衰えを見せない歌声と演奏のクオリティには「私はこんなところで終わらないぞ」と言っているような、もはや執念のようなものも感じる。
コロナ禍で配信中心のライブとなった’21は、ライン音による楽器や歌の粗が目立つアーティストが多かった中、彼らはその熟練した技術と先鋭的な機材で、しっかりとホワイトステージのトリとして貫録を見せただろう。歌は終盤でさすがに疲れを見せていたが、演奏面では圧倒されるばかりであった。彼だけでなく、「会人」にも畏敬の感情を覚えざるを得ない。
そんな御年67歳の彼だが、まだまだ精力的な活動を見せている。先述の通り、今年7月に新譜『BEACON』をリリースした。CD他、Bandcampにてデジタル音源を入手可能だ。
彼の活動をリアルタイムで見ていると、まだまだ安心する。「きっとこれからもライブをやって、フジロックのような大型フェスに出てくれるだろう」と。コロナ禍が明けた将来、配信ではない、生のライブへ必ず訪れることを心に誓った。